 悩んでいるお母さん
悩んでいるお母さん中学生の子どもが、たまに反抗的な態度をとるようになりました。
思春期のむずかしい時期なのはわかっていますが、親としてどのようにかかわっていけばいいのでしょうか。
こういった悩みにお答えします。
子どもが中学生になると、親が言ったことに対して、なにかと反抗するようになってきますよね。
小学生のときは、親の言うことをすなおに聞いていたのに…
親として正しいことを言っているのに、中学生の子どもには、なかなか受け入れてもらえなくなってきます。
なぜなら、中学生になると自分の意思や考えが強くなってくるからです。
子どもが自分の意思や考えをもち、自己主張できるようになることは、成長したというあらわれです。
ここでは、中学生の子どもがなぜ反抗するのかについてまとめてみました。
また、反抗期の中学生の子どもと親とのかかわり方について、分かりやすく解説します。
この記事を読むと、今までとは子育てのステージが変わってきたということがわかりますよ。
「反抗する」ことは子どもから大人へ近づいている証拠


中学生の子どもが、親やまわりの大人に反抗するということは、「大人に近づいている証拠」なのです。
小学校高学年あたりから、成長期がはじまります。
身長が高くなり、あっという間にママの身長を追い抜かしてしまいますよね。
子どもは、体が大きくなるだけでなく、内面の心も成長しているのです。
心の成長が「反抗する」という態度になってあらわれてくるのです。
中学生になるといつも不安定な気持ちになります
子どもの反抗的な態度は、大人になろうとしている過程で必然的におこることです。
中学生になると、まわりで起こっていることや世の中のことに、理解ができるようになります。
物事への理解が深まるとともに、自分自身のことも理解できるようになってきます。
自分がどう考えているのか、どのように感じているのか。
また、友だちや勉強、自分の容姿や能力などにコンプレックスやストレスを感じるようにもなります。
中学生になると、いろいろな感情がまざりあうことから、内面はいつも不安定な状態。
先生や親が言っていることが正しいことだと分かっていても、内面の不安定さから抵抗感をもってしまいます。
まわりの大人から指示されることにも、つい反発したくなってしまうのです。
自分の意思のほうが大切になってしまい、まわりの大人の意見にしたがいたくないという態度につながっていくのです。
子どもから反抗されると、親は戸惑ってしまいますけどね…
精神的に自立しようともがいているものの、まだ中学生。
実際は、経済的にも生活面においても、親に依存しなければいけない状況です。
親にたよりながらも、精神的には自立したいという中途半端な気持ちからも「反抗的な態度」につながるのです。
子どもの反抗的な態度は、大人に近づいていく過程で起こることなのです。
反抗することは自立への第一歩
反抗することは、親から精神的に自立しようとしている第一歩です。
小さいころから物分かりがよく、あまり反抗しない子どもは、親の手がかかりません。
しっかりして、自立しているように感じますよね。
物分かりがいいということは、「自分の意見をもっていない」ということがあります。
まわりの人の意見や指示に、したがっているだけかもしれません。
自立しているのではなく、自分で考えて行動していないということです。
自分の考えをもつことなく、自立心がない大人になってしまうことがあります。
自立心がない大人が社会に出てしまうと、かならず壁にぶつかり、立ち止まってしまいます。
困難な状況にあたると、自分で考えたり、解決するために乗りこえたりする力がないのです。
子どもの自立には反抗することが必要だと分かっていても、親は戸惑ってしまいますよね。
ついこの前までは、すなおに言うことを聞いていたのに…
親であれば、そう思ってしまいがちです。
子どもの内面は、どんどん成長し、これからもいろいろなことを吸収していくことでしょう。
反抗期は、自立しようともがいている途中で起こること。
子どもが反抗することは、ずっと続くわけではありませんので、あまり不安にならなくても大丈夫です。
反抗することは、子どもの成長にとっては大事なステップのひとつなのです。
自立するために親ができること:2つ


子どもが中学生になると、今までの親子関係では通用しなくなります。
子どもの内面が、大きく成長しているためです。
子どもが親に反抗するようになるのも、成長のひとつ。
親の保護からひとり立ちしようとし、自分を確立するために反抗しているのです。
今までの親子関係を見直し、新しい関係に作りかえてみましょう。
中学生の子どもをもつ親が、自立させるためにできることは2つです。
- 子どもを「ひとりの大人」として扱いましょう。
- 子どもに干渉しすぎるのはやめましょう。
子どもを「ひとりの大人」としてあつかいましょう
反抗するということは、子どもから大人になろうとしている途中です。
今までの親子関係は、親と「子ども」でした。
これからは、子どもではなく「ひとりの大人」としてあつかいましょう。
中学生になると、自分のことやまわりのことを考え、判断ができる年齢です。
さらに、自分の意思や考えを、しっかりともつことができます。
親が子どもの意思や考えをさまたげてしまうと、子どもの自立心が育たなくなってしまいます。



「夜更かしせずに、早く寝なさい!」
「ごはんを食べる前に、宿題をやりなさい!」
小学生のときと同じように、子どもについつい言ってしまいたくなりますよね。
中学生になれば、宿題をやらなければならないことも、生活のリズムも分かっているはずです。
口には出さないけど、「〇時には宿題をやろう」と考えているものです。
自分なりの考えがあるのに、親から指示されると、イヤな気持ちになるのも分かりますよね。
もし、宿題をせずにそのまま学校に行ってしまったとしても、責任は子ども自身にあります。
大人になるということは、自分の行動に責任をもつことでもあります。
宿題は自分でするもの、しなかったとしても親の責任ではありませんよ。
学校でこまるのは、子どもなのです。
子どもをひとりの大人としてあつかい、子どもの意思や考え方を尊重してあげてください。
親の価値観や判断を押し付けてしまうと、子どもは受け入れようとはしません。
親は、子どもの言動を受け入れるゆとりを持つように、心がけてください。
これからは、子どもをひとりの大人としてあついかい、対等に話し合える関係をきずいていきましょう。
子どもに干渉しすぎるのはやめましょう
過干渉というのは、「親がこうした方がいいと考えることを、子どもにしてあげる」状態のことです。
親は、子どものためにと思ってやっているつもりかもしれません。
「転ばぬ先の杖」のように、先のことを考え、親が手を出してしまうのは好ましくありません。
過干渉は、子どものためにはならないのです。



子どもが忘れ物をしないように、時間わりのチェックをしてあげています。
定期テストの前には、勉強の計画を立ててあげています。
子どもは成長しているのに、親は変わらず子どものことに手を出してしまうため、さらに反抗されてしまうのです。
とくに、中学生になると、親からの干渉を嫌うようになります。
親が勝手に、子どもの世界へと入りこんでいるようなものです。
過干渉をつづけてしまうと、自立しようとしている子どもの妨げになってしまいます。
自分でできることは、自分で取り組ませてください。
もし、親が子どものためにと思い、やってあげていることがたくさんある場合は、少しづつ減らしていきましょう。
親が子どもの生活に干渉しすぎると、子どもはいつまでも甘えてしまいます。
子どもは、ひとりでは決められず、何もできなくなってしまいます。
親はできる限り、手を出さないようにしましょう。
子どもがアドバイスなどを求めてきたときが、親の出番です。
親が子どもの話を受けとめ、問題解決できる糸口を見つけるようにアドバイスすることが、子どもの自立のためになります。
中学生になっても反抗期がない子どももいます





うちの子は、反抗するような態度をとらないんだけど、自立できない大人になってしまうの?
反抗期がこない中学生をもつ親は、心配になるかもしれません。
反抗期がない子どもには、3つのパターンがあります。
- 子どもの性格
- 親と子どもの関係
- 子どもが自己主張できない
子どもの性格が、おだやかで天真らんまんな場合は、反抗しても目立たないということがあります。
子どもとしては反抗している態度であっても、親がさほど反抗していると感じていないということです。
また、もともと親子の関係が良好な場合も、反抗しても分かりにくいことがあります。
親が子どもとほどよい距離をとりながら、よく話をし、分かりあっているためです。
子どもが反抗したとしても、親はそれほどのこととは感じていないのです。
最後の「子どもが自己主張できない」という場合は、注意が必要です。
親が子どもを管理し、コントロールしているため、反抗できないということです。
子どもは、自分を確立する大事な時期に、自己主張ができない状態がつづきます。
自己主張ができないと、自立心が育たないまま大人になってしまいます。
自分で考え、行動できないまま大人になってしまうと、社会に適応できない可能性が高くなってしまいます。
まとめ


子どもは、10歳を過ぎるあたりから内面的に成長していきます。
子どもから大人になる階段を、一段ずつのぼっている途中なのです。
親としてできることは、大人へと成長している子どもを見守り、サポートしてあげることです。
反抗した態度をとっていても、子どもが成長するとともに落ち着いてきます。
それまでは、子ども自身が自分の力で乗り越えられるように、親が支えることが子どもの自立につながるのです。


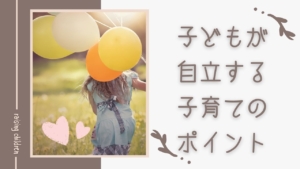
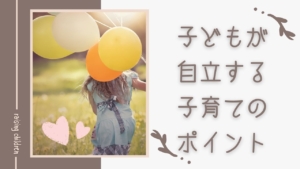


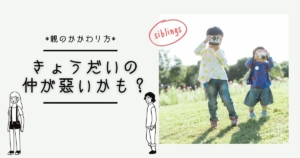


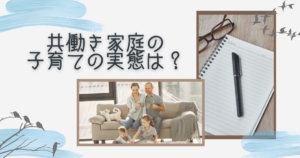
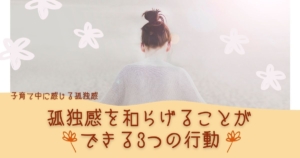
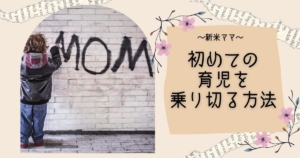
コメント